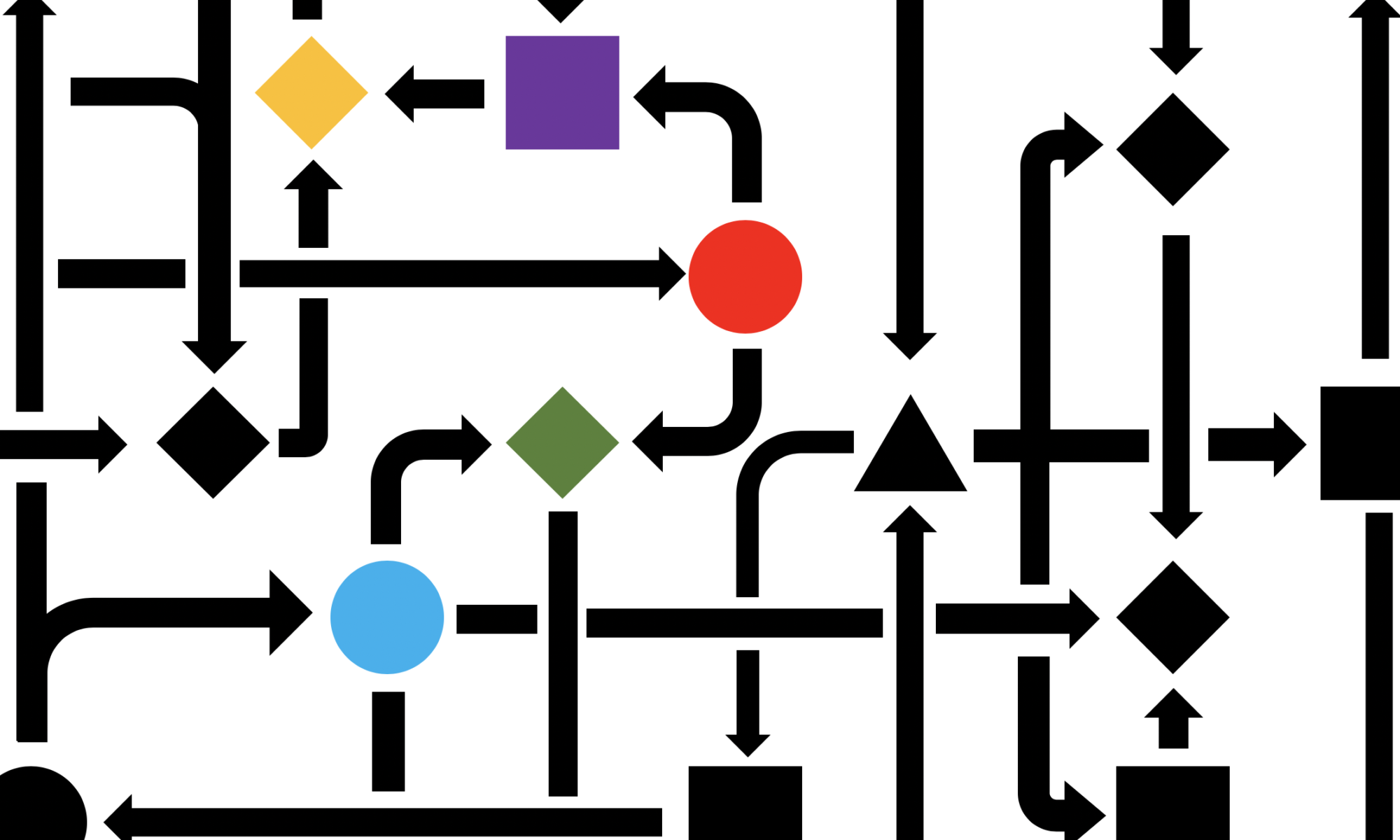自己愛不全者の行動に共通する構造に「求められていないのに一方的に提供する」というものがある。彼らは「何かをやらないと居ても立ってもいられない」という心理状態で日々行動している。それは例えば仕事上の業績追求行動、個人ブログやSNS等での情報発信につながる心理である(このブログもそうした心理の結果であることを否定しない)。それらはよく観察すると、実は誰からも求められたわけではないことに気がつく。
ガス抜きの方法、二面性、自己愛憤怒
理性的行動と感情的行動
感情的な人間は感情による納得行動を理性による納得行動で上書きできない。自己愛に駆られた無意識の行動は、その健全/不健全を問わず感情的な納得行動に類する。理性による納得行動を習慣化することで、よい結果が生まれることが体感され、同じ行動であっても理性的行動が感情的行動に変化する。我々は生まれつき、理性よりも感情に行動を規定される。それがすべての動物の本性である。理性はしばしば、自己愛不全のある者がある種の代償行動(理論的思考を要するような学問の追究)に没頭する過程で発達する。そういう者は、自己愛による不健全な感情的納得行動から脱却する術を手に入れたという点では幸運である。だが優しさや親切心の体験を通して健全な感情的納得行動を人生早期に身に付けることができた者は、理性をさほど発達させなくとも幸福な人生を歩むことができる。彼らは自分の健全な感情的納得行動を理性で上書きする必要がない。最も不幸なのは、人生の早期に優しさや親切心に触れることができず、さらにそこから生じた自己愛不全を理性的行動以外の手段ばかりで補償してきた者たちである。自分を美しく見せることや、「特別」に見せることへの没頭に理論的思考は必須ではない。この視点では、美容整形により自分をいつまでも若く見せることに執心する者も、何冊も学術書を出版して名声を得る者も本質は同じである。社会的評価や地位は、どのような自己愛不全解決策を選んだかの偶然の産物でしかない。
感情による納得と医療
私たちの行動様式は、主として感情的な納得に基づいている。他人に親切にする温かさを知っているから他者に親切にする。これはポジティブな感情体験による行動様式の内面化である。理想的には行動様式のすべてがポジティブな感情体験に基づいているのがよく、その人は極めて人間的な、温かい行動から健全に自己愛を補給できる人物になる。ご飯を食べこぼしたら強く叱られたから自然と食べこぼさなくなる。これはネガティブな感情体験から学習された行動様式である。実際には多くの行動様式が恐怖や罰によるネガティブな感情体験により内面化されている。しつけというのは往々にして恐怖を用いた道徳の内面化である。迷惑な行動をして親から怒鳴られ、叩かれるからその行動を避けるようになる。道徳的行動をポジティブな感情体験から内面化させるしつけは非常に難しい。いずれにしても、これらの行動は本人が「心から」納得したものであり、規範意識とは異なる形で本人の真の人格を形成する。規範意識とは、感情的納得を伴わない「押し付けられた」道徳のことだと私は考えている。それは内面化されていない道徳であり、その人の人格の外側にある。その人がいくら「優しい」行動をしているように見えても、本人が「優しくしなくては」と考えて行動しているとすれば、その行動はどこか自然さを欠き、その人は真に優しい人ではない。
研修者の心得
1.学習の本質
医学教育において、初期研修とは軸を持たない者に正しい軸を持たせる段階である。初期研修医はほとんどの場合、自らの診療の軸すなわちポリシー、ものの考え方、信念が確立していないため、決断に自信が持てず優柔不断であり、診療の「結果」からしか自らの診療行為を評価できず、行為の成否に自己評価が左右される。この結果主義的態度を次第に過程主義へと変化させていくのが正しい教育の方向である。この方向性はERやICUでの教育に限ったことではない。初期研修を通して、またその後の生涯学習においても、正しい診療信念の確立とその洗練が学習の本質である。
患者に化粧をして満足ですか?
「数字を治療するな。患者を治療しろ。」
医師としてこのような説教を誰しも耳にしたことがあるでしょう。実際のところ、我々は治療指標の多くを目の前にある数字に頼っています。血圧、心拍数、SpO2、体温、カリウム値、クレアチニン値、ビリルビン値、白血球数、、、ただしそれらの数字には、治療対象として妥当なものもあれば、そうでないものもあります。
“患者に化粧をして満足ですか?” の続きを読むなぜあの人がムンテラするといつもFull CPRになるのか
急性期医療の現場では、しばしばこの種の問題に直面します。寝たきりの高齢者に人工呼吸器を装着する、透析を回す、胸骨圧迫を行う、、、適切な医療ではないと何となく感じていても、患者さんや家族の要望通りにしてしまう、結局いつも積極的治療を選択してしまう。これらのどこに問題があり、そして解決方法はあるのでしょうか?
“なぜあの人がムンテラするといつもFull CPRになるのか” の続きを読む診断と真理 〜「肺炎か否か」はどうでもいい?病気を「治療する」ということ〜 第3回
3回にわたって、我々が日常診療で行っている「診断」というものの本質について考えていきます。よく言われる「診断にこだわる」姿勢は、医師として大変素晴らしいもののように聞こえます。しかし、それは果たして病気を治療する上で常に正しい態度と言えるのでしょうか?
“診断と真理 〜「肺炎か否か」はどうでもいい?病気を「治療する」ということ〜 第3回” の続きを読む診断と真理 〜「肺炎か否か」はどうでもいい?病気を「治療する」ということ〜 第2回
3回にわたって、我々が日常診療で行っている「診断」というものの本質について考えていきます。よく言われる「診断にこだわる」姿勢は、医師として大変素晴らしいもののように聞こえます。しかし、それは果たして病気を治療する上で常に正しい態度と言えるのでしょうか?
“診断と真理 〜「肺炎か否か」はどうでもいい?病気を「治療する」ということ〜 第2回” の続きを読む診断と真理 〜「肺炎か否か」はどうでもいい?病気を「治療する」ということ〜 第1回
3回にわたって、我々が日常診療で行っている「診断」というものの本質について考えていきます。よく言われる「診断にこだわる」姿勢は、医師として大変素晴らしいもののように聞こえます。しかし、それは果たして病気を治療する上で常に正しい態度と言えるのでしょうか?
“診断と真理 〜「肺炎か否か」はどうでもいい?病気を「治療する」ということ〜 第1回” の続きを読む